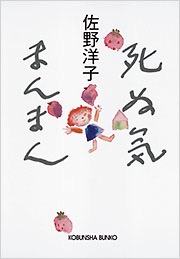『死ぬ気まんまん』佐野洋子
おはようございます😉
図書倶楽部
『死ぬ気まんまん』佐野洋子
自身の乳ガン闘病を綴った最後のエッセイ。表題の意味がが直接的にホントかどうかは別として、死を恐れず、受け入れてる。「闘病記が嫌いなの」「やめろよ、壮絶なんて、さっさと死ねよ」と語る。
洋子さんが学んだことは、全て貧乏からだった、金持ちは金を自慢するが、貧乏人は貧乏を自慢する。皆、何かを自慢しなければ生きていけないのか。大切なのは「情」と言うものだった。
他人の死は精々、一時間しか続かない。親族と他人は違うんだ。特に仲の良かった人以外は、時々思い出してその人のことを想えれば上等なのかも知れない。
死に対する感じ方には、”一人称(自分)”二人称(親族)”三人称(友達、他人)”がある。死んだ後に一番深刻なのは”二人称”で一人称は死ぬまでが深刻なのだ。死は最後の経験でそれを誰にも教えられない。
延命治療はしないで欲しい。ただ、痛みだけは取ってもらいたい。モルヒネを使う前には、会いたい人には会って、会うのは無理な人にはせめて手紙でもいいから今までの感謝の気持ちを伝えたい。
様々な経験を通じて、自分なりの死生観を持つということは、大切なことなのかもなと感じる。
佐野さんの闘わない病生活は、ユーモアに溢れ、でもせつなくて、やっぱり最後は悲しくて、ホロリとしてしまう、佐野さんの絵本のような話しだった。中でも印象残ったのは、癌になったら誰もが優しくしてくれた、精神を患った時はみな離れていき、そちらの方がよほど辛かった、と言う言葉。精神を患うと別人と見なされるのだろう。
神も仏も信じなかった洋子さん、信じるものに対する揺るぎない強さに、共鳴と憧れを抱いた。責任を持つが故の発言の鋭さと共に、人生や病気の辛さ、人としての情も深く感じられ、とても豊かな人だったのだなと偲ばれる。
一般的に、50歳までは遺伝子が生存.生殖モードでプログラムされているので、殆どの人は平等に元気に仕事が出来るが、この先に個人差が大きくなる、生活習慣により状態の良い人と悪くなる人に。
現代人の生活は生物学的なものと相対するように動いている。生物として自然の摂理に合わせて精一杯生きて、死んで行く事が、人間としても最も幸せなことと満足するのが必要だと想う。